えっ、補償額って憲法で決まってるの?」最大判昭和28年12月23日のお話
🧾Hasu超訳
農地改革の一環として、政府が「自作農創設特別措置法」に基づき農地を買収しました。 しかし元の所有者は、「買収価格が安すぎて、憲法29条3項の“正当な補償”になっていない!」と主張し、補償額の増額を求めて訴えました。
でも最高裁はこう言いました。
「補償額は、その時代の経済状況に基づいて合理的に算出された“相当な額”であればOKなんだよ」
つまり、完全な市場価格でなくても、合理的な根拠があれば憲法上の“正当な補償”と認められるということです。
この判例は、「財産権の保障」や「公共の福祉とのバランス」について考えるうえでとても重要!行政書士試験でも頻出なので、要チェックです!
📝裁判のざっくり要約
昭和28年12月23日、最高裁は「農地買収に対する補償額が憲法29条3項に適合するか」が争点となった事件で判決を下しました。
争点は、「自作農創設特別措置法で定められた買収価格が、憲法で保障された“正当な補償”にあたるのか?」という点。
最高裁は、「その時代の経済状況に基づいて合理的に算出された価格であれば、憲法上の補償として十分」と判断しました。
📌判決のポイント
- 憲法29条3項は、財産権の公共利用に対して「正当な補償」を求めている。
- 「正当な補償」とは、合理的に算出された相当な額であり、必ずしも市場価格と一致する必要はない。
- 自作農創設特別措置法の買収価格(賃貸価格の40倍など)は、法律の目的と経済状況に照らして合理的。
- よって、当該買収価格は憲法29条3項にいう「正当な補償」にあたる。
この判例は、補償制度の限界や、財産権と公共の福祉のバランスを示す重要な判断です。
この判例の詳細は、裁判所の公式判例検索ページで確認できます。
✎理解度テスト
最大判昭和28年12月23日の判例において、「正当な補償」として認められる条件として正しいものはどれ?
①常に市場価格と一致すること
②所有者が納得する価格であること
③合理的に算出された相当な額であること
④補償額は法律で一律に定めること
答えは↓スクロール
>
>
>
>
>
>
答えは③です。
一言解説:「正当な補償とは、合理的に算出された相当な額であり、市場価格と完全に一致する必要はありません!」
今日のひと頑張りが、明日の私をつよくする!!
ありがとうございました✿
Hasu
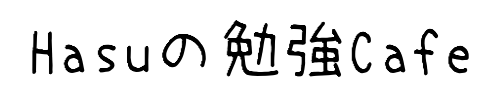
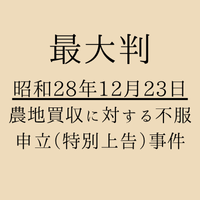
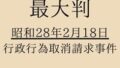
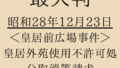
コメント